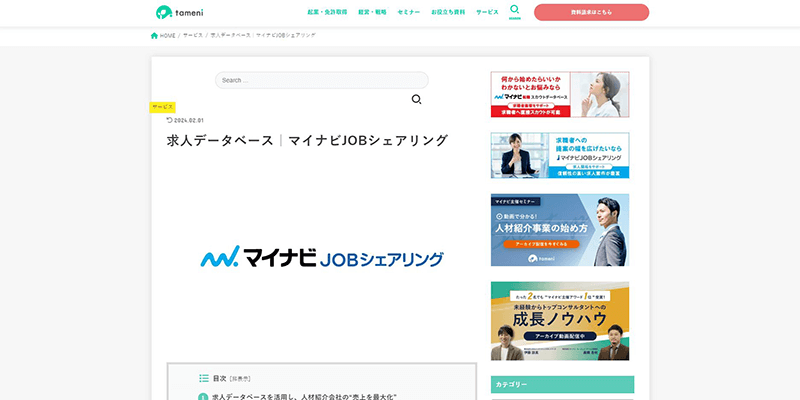人材紹介の免許取得を解説
本記事では、人材紹介業を営む上で免許(許認可)が必要な理由についてわかりやすく解説。登録要件や手数料、必要書類、登録の流れ、注意点についても紹介しています。
免許(許認可)が必要な理由
人材紹介業は、厚生労働省が管轄する「許認可事業」に指定されています。これは、有料で職業紹介を行う企業の不当な中間搾取を防ぎ、労働者の権利を守るためです。
免許(許認可)を取得している人材紹介会社は、法律に則って事業を運営していることが保証され、顧客からの信頼獲得につながります。
無免許(無許可)で人材紹介業を営んだ会社には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。人材紹介業を営む際は必ず免許(許認可)を取得しましょう。
参照元:厚生労働省「第14違法行為による罰則、行政処分」【PDF】
(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/dl/14.pdf)
人材紹介業の登録要件
財産要件
人材紹介会社を立ち上げる際は、「総資産額-負債額=500万円以上」の資本金が必要です。
また、資本金500万円のうち、「自己名義の現金もしくは預貯金が150万円以上ある」ことも必須要件となっています。
500万円をすべて融資で賄う場合は必須要件を満たせません。
人材紹介会社の起業に必要な資金や抑えるべきコストについて詳しく見る
職業紹介責任者の選任
人材紹介事業を始める前には必ず職業紹介責任者講習を受講し、「職業紹介責任者」の資格を取得します。
職業紹介責任者は基本1事業所につき1名の選任となりますが、職業紹介従事者50名を超える場合は、従業者50名につき1名以上の選任が必須です。
また、選任対象の人物は「3年以上の就業経験のある成人」が必須要件となっています。
オフィスの要件
職業柄、個人情報やプライバシー関連の情報を多く取り扱うため、その情報を守るオフィスの要件も設けられています。
オフィスでは個室を用意したり、パーテーションで区切ったりするのが基本です。位置や構造など複数の決まりがあり、条件を満たしている場合は適正なオフィスとして認められます。
参照元:厚生労働省「有料職業紹介事業 許可要件(概要)」【PDF】
(https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/content/contents/001694168.pdf)
個人情報保護に関する要件
令和4年10月に職業安定法が改正されたため、個人情報の取扱に関する規定の変更がありました。
職業紹介事業者は、求職者の個人情報を業務の目的達成に必要な範囲内で収集・保管・使用しなければなりません。厚生労働省令で定められた通り、求職者に対して個人情報の使用目的を明らかにする必要もあります。
事業所では、個人情報を扱うスタッフを明確にし、情報共有に線引きをするなどの対策も有効です。また業務と関係のない個人情報は廃棄するなどして対処しましょう。
免許(許認可)の取得にかかる手数料
人材紹介事業の免許を取得するには、登録免許税(9万円)と収入印紙代(5万円)がかかります。
人材紹介会社の立ち上げに必要な定款認証の費用は別途発生するため、資金不足にならないよう注意しましょう。
費用は 許認可申請のみにかかる手数料です。実際に人材紹介業を立ち上げる際には、この他に「定款認証」なども必要となります。
法人登記等にかかる費用はどれくらいか
法人登記の準備をする前に、「職業紹介責任者講習」を受講する必要があります。受講費用は8,800円〜13,000円前後となります。
また法人登記の費用の目安は、自分で行う場合は10〜15万円程度。法人登記を代行業者に依頼する場合は、30万円前後かかることがあります。
オフィス費用も計算に入れておく
人材紹介業を行うには、厚生労働省が定めるオフィス開業の要件を満たす必要があります。しかし2017年の法改正により要件が緩和され、レンタルオフィスや住宅用マンションなどでも開業が可能となりました。
ただし将来的にキャリアアドバイザーやリクルーティングアドバイザーの採用を考えているなら、オフィスへの入居が必要です。
地域によってオフィスの賃料は異なりますが、東京23区の場合は敷金・礼金を含めて約100万円ほどの準備が必要でしょう。
免許(許認可)の取得に必要な書類一覧
- 有料職業紹介事業許可申請書(3部)
- 有料職業紹介事業計画書(3部)
- 届出制手数料届出書・手数料表(3部)※届出制手数料を採用する場合のみ
- 職業紹介事業取扱職種等届出書(3部)※職種・地域を定めて届け出る場合のみ
上記以外にも添付書類が複数あるため、不備がないように準備しましょう。
免許(許認可)取得の流れと注意点
免許(許認可)を申請した日から許可証交付されるまでに、およそ2~3ヶ月かかります。
不備があると始めからやり直すこともあるため、準備とスケジュールには余裕をもっておきましょう。
- 許可申請(要件を満たしているか確認)
- 職業紹介責任者の受講
- 書類準備・作成
- 労働局にて確認し、捺印後に申請手続き
- 事業所の検査
- 許可証交付
許可取得後・運営開始フェーズで押さえるポイント
許可取得はゴールではなくスタートです。登録後すぐに事業を軌道に乗せるためには、法令遵守と業務オペレーションの整備を両輪で進める必要があります。
1. 事業開始届け出と定期報告
厚生労働省への事業開始報告書を提出後も、毎年度の事業報告・財務状況報告が義務付けられています。期限内(通常は翌年度6月末)に提出しないと、行政指導や許可取消のリスクが生じるため注意が必要です。
2. 労働者情報の適正管理
求職者の個人情報は個人情報保護法や職業安定法に基づき厳格に管理します。取得目的の明示、保管期間の規定、第三者提供時の同意取得など、社内ポリシーを策定し従業員に周知徹底しましょう。
3. 紹介手数料・契約書類の整備
紹介手数料率は自由化されていますが、約款として明示する義務があります。
また、求人企業・求職者の双方と紹介契約書を結び、手数料や返戻規定を明記することで、トラブル防止とコンプライアンスを両立できます。
4. キャリアコンサルタント体制と教育
職業紹介責任者だけでなく、実際に面談を行う担当者にもキャリアコンサルティング技能を身に付けさせることで、サービス品質が向上し早期離職リスクを低減できます。
厚労省が推奨する職業能力開発促進法に基づく研修や民間資格の活用が有効です。
5. 求人・求職データベースの活用
立ち上げ初期は紹介案件数が限られるため、求人データベースやスカウトプラットフォームを利用し、候補者プールと求人を拡充するのが近道です。
クラウド型ATSとの連携により、マッチング精度向上と業務効率化を同時に実現できます。
6. PDCAサイクルによる業務改善
紹介後3ヵ月・6ヵ月定着率、候補者満足度、クライアントリピート率などKPIを設定し、評価・改善を繰り返すことで収益性と信頼性が向上します。
人材紹介業の免許取得・許認可申請・登録時で起こりやすいミスと対策について
オフィスの個室や書類の保管に鍵が必要な場合がある
最近ではオープンな空間のオフィスデザインが増えていますが、人材紹介業の免許取得要件においては開放的なオフィスはマッチしないケースがあります。
人材紹介業では個人情報を扱うため、求職者のプライバシー保護が不可欠です。ほかの求職者と同じスペースにいるリスクがあったり、十分なプライバシー保護がなされないと判断されると、免許取得ができないことがあります。
求職者と面談するための個室を用意し、鍵がかかればより良いでしょう。
またオフィスビルのセキュリティや社内の書類保管体制が万全でないと、書類保管スペースにも鍵の取り付けが必要になるケースもあります。
全てのレンタルオフィスで免許が取得できるとは限らない
免許取得に求められるオフィス要件が緩和され、レンタルオフィスや住宅用マンションでも開業できるようになりました。しかしながら、レンタルオフィスなどであっても区分けされた面談スペースがあるなど、個人情報やプライバシー保護ができるスペースが必要です。
レンタルオフィスなどで免許申請を行う場合には、個室または区分けされたスペースがあり、会議室としてレンタルができるかどうか、執務スペースとして個別ブースの契約ができるか、鍵のかかる金庫やロッカーが利用できるかなど、オフィス要件を満たせるか確認してください。
資産要件は「現金500万円があれば十分」というわけではない
人材紹介業の新規立ち上げ時には「総資産額-負債額=500万円以上」の資本金が必要です。しかしこれは「現金500万円があれば良い」という意味ではありません。
実際には、「資産総額から負債を差し引いた金額が500万円を超えており、かつ事業資金が現預金で150万円以上」である必要があります。
すでに金融機関から借入をしている場合には負債とみなされるため注意してください。
まとめ:重要なのは免許取得・起業した後の「求人開拓」
免許(許認可)を取得するのは大前提として、その後事業が成功するかどうかは「立ち上げ後の求人開拓」にかかっています。
求人開拓の期間が長引けば資金ショートにつながりますし、開拓した求人数が少なければ求職者の集客も難しくなるためです。
免許取得後、良いスタートダッシュを切るためには、求人案件がクラウド上にすべて集約されている求人データベースの活用がおすすめ。
導入すれば求人開拓にかかる工数を削減でき、求職者フォローにあてられるため、他社と差別化を図れるでしょう。
当サイトではおすすめの求人データベースを紹介しているので、免許取得後の成功を見越している方は参考にしてみてください。
【ニーズで選ぶ】
求人データベース3選を見る